第16話 " 夜のインスブルック "
今回は夜のインスブルック散策です。夕暮れ時の駅前に人々が集まって、行進が始まるのを今か今かと待っています。何かしら記念日やお祭りがあると、オーストリアやドイツで村人がそれぞれ楽器を持って演奏しながら行進している風景を良くテレビで見ますね。

先頭にはバトンガールが持つような指揮棒を持ってハンサムな青年。二番目には、左右に女の人が二人、その後ろに合奏隊が、チロルの上着に皮の半ズボン、羽根の着いたチロルハット、お揃いの民族衣装で並びます。観光客のフラッシュを浴びて、指揮者は少しはにかんでいます。
二人の女の人が小脇に抱えている小さなビヤ樽には、ビールではなく、非常に強い、独和辞典に「火酒」と訳されている、ウォッカのような透明の地酒、シュナップスSchnapsが入っています。見物人の中で所望する人がいると、行進から離れて、彼女の持っている小さなグラスにコックを開けて注いでくれます。(有料です。)私などは、鼻をグラスに近づけただけで、立ちぼってくるアルコールに「ウーッ」とせき込むほどでしたが、団長はおいしそうに飲み干していました。
行進について歩いたりすると、観光旅行している実感がわいていきます。夜のインスブルックは、目立つネオンサインもなく、平然とした様子は、昼と変わらず、好感が持てました。案外規制なんかあるのかも知れませんね。…………
今度は、さらに観光満載の場所に案内されました。団体旅行の場合、次にどこに行くか、何をするかを、充分に把握しなくても、塊から離れなければ無責任に旅を楽しむ事が出来ますが、その時の私も、そうでした。
小さな暗い廊下を通り、階段を登り、ドアを開けるとワーッと音楽が溢れてきました。
舞台でくりひろげられているのは、まさしくチロルの世界。ヨーデル、アルペンホルン、チロリアンダンス、男の人が、足の裏や、太股を強くうちながら飛び跳ねて踊る独特の踊り。等々。
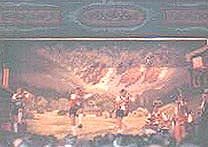
その国旗に該当するお客さんのグループから拍手がわき起こります。私達は行進について歩いて、遅れて入ってきたので、最後部の席ですから、前の方で、部分的に盛り上がるのが、よく見えます。今日のお客がどこの国の人なのか、ちゃんと報告がいっているらしく、すぐに、誰もが知っている代表的なその国の唄が何曲か演奏されます。私の知っている「庭の千草」もありましたが、覚えている旋律が部分的に違い、原曲と日本化された曲では受ける印象が随分と違うんだ、と不思議な気持ちで、音の洪水に身をゆだねていました。
そのうちに星条旗があがりました。さすがアメリカ、スゴイ盛り上がりです。おじさんやおばさんばかりなのに、総立ちで揺れながら一緒に歌っています。私が日本で似たような光景を見たのは、阪神タイガースが優勝した夜の大阪の町での「六甲おろし」の嵐、ただ一回です。
ついについに、小さな日の丸が上がりました。我々はお互いニコニコしながらも、拍手もまばら。別に誰に気兼ねすることもないのに、シーンとしています。数では、アメリカに負けないのに、派手なアメリカの後では、大幅に見劣りします。誰一人立ち上がらず、誰一人歌いません。「さくら、さくら」は、我々のテーマミュージックみたいなもので、食後の"Sakura Time"にいつだって歌っていて、歌詞も完璧なのに。
要するに恥ずかしい。 感情表現は"恥"。 Shyで盛り上がれない。
人々は、なんておとなしい国民だろうと思ったでしょうね。人殺しだっていっぱいあるのに。
10年ほど前、南ドイツ・ミュンヘンの、ビアホール『ホッフブロイハウス』、(部屋はチロルの数倍の広さですが)でのことです。同様の、観光客向けのショーが行われていました。たくさんの日本人がイタリア人に混じって長い列を作り、音楽に合わせて、ホール中を練り歩いているのです。こんなにも簡単に日本人が変われば、日本での常識も変わって来るはず。ちょっとたじろいで仕舞いました。
スイスでも同様の民俗芸能を見ました。お土産と同じように、これらが、本来どこのものなのか、あるいは微妙な違いがあるのか、いまだに分かりません。
表向き傍観者のような態度でいた私を、このチロルのショーは十二分に楽しませてくれました。観光客に媚びを売るような、わざとらしい物を、現地の人はきっと胡散臭そうに見ているでしょうが、それもまた楽しいのは、通りすがりの外国人観光客であるからでしょうか。
日本に来た外人さんは、「舞妓さんの踊りを見てみたい。」なんて思っているかも知れません。舞妓さんが今日の日本を表現していると、殆ど言えなくても。
自分の中で、あるいは自国で、そこに抱いたイメージ(多少のズレがあっても)を肯定してくれる物がないと、「来た。」という証拠が心に作れない様な気がします。
ビルの林立する都市はどこでも概ね同じ様な表情をしていて、そこにある一流のホテルは、同じ安らぎを提供してくれるでしょうが、旅した実感として後まで残るのは、案外土臭い物や、受け入れがたい味や、固いベッド、そして人の温かいもてなしなのです。
旅の毎日で、このような土俗文化を含めて、今と変わりのない生活様式を知り、オーストリアの文化もまた、明治の日本が受け入れた西洋文明の源流の一つであり、元祖だと思えました。
