第24話 " オーストリアワイン の故郷 "
![]() 葡萄畑・・・・・・・・
葡萄畑・・・・・・・・
その頃、よくテレビに出てくる外国と言えば、パリかロンドンかスペインか・・・、エッフェル塔や、二階建てバス、闘牛士など、つまりそれが映ればそこと、誰でもが解る有名な場所ばかりで、ヨーロッパの田舎が映ることは滅多となく、まして言葉も不確かな一人の若者が、土地の人との交流を深めて、帰るときには涙ながらに抱き合う、などという情景は全く見られませんでした。
通り一遍に、観光地をつまみ食いするような、パック旅行が海外旅行の定番だった時代、『私のオーストリア旅行』は実に、このような心のふれあう "旅" の経験だったのです。現地の人たちとは、お互いに外国語(英語)で話しているわけですが、理解し合おうとするとなんとかなる。ほんの小さな出来事も今も鮮烈な情景として、懐かしく大きな感動を伴ってなってよみがえってきます。
ニーダーエステライッヒ州Niederoesterreichには、葡萄の生育に適したなだらかな丘陵地帯があり、オーストリアワインの故郷の一つとなっています。知名度はドイツワインに一歩譲るところですが、オーストリアワインもさっぱりした味わいの白ワインがなかなか美味です。
TVで、収穫期のドイツの葡萄畑を見たことがありますが、あちこちからやって来た若いアルバイターが、農場主に混じって、大きな角笛型の背負子を背負って手作業で葡萄を収穫していました。
日本で言えば茶摘みのような感じでしょうか。葡萄の木の間を人が動いて籠が一杯になればうつむいて、トラックにあけ、トラックは工場へ帰り葡萄は機械で圧搾されてワインの元のジュースになります。皮をむけば白ワイン、皮をむかずにそのまま絞れば赤ワインになるそうです。
勿論それは秋のこと。今は真夏。日なたにいれば汗ばむ程の太陽の光りを存分に浴びて、畑全体、そして山から山へ葡萄の木が青々と繁っていました。低い棚状に作られた葡萄畑の足元は、草もまばらでよく手入れされた、大変きれいな土の色が見えていました。
ちなみに、1975年のヨーロッパの夏はまれにみる暑さで、植物の生育が非常によく、この年のワインは上質だという噂です。巷ではお目にかかったことはありませんが。
![]() ヴァインケラー 〔Weinkeller〕・・・・・・・・
ヴァインケラー 〔Weinkeller〕・・・・・・・・
「葡萄酒貯蔵用穴蔵」です。英語で "winecellar" つまり地下にあるワインを飲ませる酒場を意味する事もありますが、ここでは文字通り葡萄汁が静かに眠りワインに変身する場所のことです。眩い夏の光りの中からいきなり裸電球のつく、暗い半地下の部屋に入りました。きっと昔は蝋燭の光りだけが頼りだったのでしょう。暗い中に黒い物があるようなのですが・・・。それはやがて、私達の背丈より大きい木の樽だと解りました。いくつも並んで、その中にワインがじっとおいしくなる時を待っています。
かつて子供の頃、親類の家の蔵で似たような光景を目にしたことがありました。それは昔使っていた、醤油作りのばかでかい樽で、戸を開けた瞬間なんて狭い部屋だと思ったらそれが、二階までの高さのある樽の側面だったのです。醤油蔵にはさんさんと太陽が降り注いでいましたが、このワイン蔵はあくまで暗く、冷たく、狭く、天井も低く押しつぶされそうでした。案外ワインはネクラなヤツカモね。
我々の間をすり抜けながら、その道のマイスターか、大きな男の人が梯子を使って、ワイン樽に登ります。樽の天井部には小さな穴がうがたれているらしく、1mはゆうにあろうかという長いガラスのスポイトのお化けのような物を慎重にその穴に差し込み、これは○○、次は○○と熟成中でまだ未完成の我々のような(?)ワインをグラスに少しずつ注いでくれます。もったいないから、聞き酒のように捨てたりしません。全て義理堅く飲み干していけば、後は野となれ山となれ・・・。
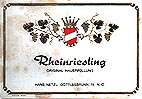
ワインの味を支配するのは元になる葡萄の種類ですが、気温、傾斜地の水はけの問題、病気に強いなどからドイツではリースリング種の葡萄がよく育てられていますが、オーストリアでは、グリューナー・ウ゛ェルトリーナ種が多いようです。ワインのラベルには、含まれている主な葡萄の種類も書かれています。ここで飲んだマスカットだけで出来た白ワインの味を私は今も忘れることが出来ません。お土産にした同じワインは、帰国後すぐに無くなりましたが・・・、それ以来飲んだこともありません。
葡萄はドイツ語でTraube〔トラウベ〕です。複数形でTrauben オーストリア人の発音では〔タウベン〕と聞こえます。熟するとほんのり紫の部分もある薄黄緑色の、大きさは巨峰ぐらいのもので、皮が薄いので、向こうの人はそのまま、ポイ、ポイッと口に放り込んで種も一緒に食べてしまいます。いちいち皮をむいて食べ、最後には舌の先にプツッと種を吐き出す丁寧な私を「とんでもない贅沢をするヤツだ」と言うかわりに、「信じられない」と言って驚いていました。私が皮をむくのは、皮についているかも知れない農薬が心配な事もありますが、彼等は気にしていない様子。ヨーロッパの果物がすべて "無農薬栽培" ということは無いと思うのですが。
![]() ホイリゲ 〔Heurige〕・・・・・・・・
ホイリゲ 〔Heurige〕・・・・・・・・
もう一つ忘れてならないのは『ホイリゲ』、元々新酒の意味ですが、それを飲ませてくれるお店を言います。ドイツのビヤホールのように騒然としていないし、人々が声高に論議をしているわけでもない。さすが優雅な音楽の国オーストリア、時代色のついた部屋の中や外の庭で、生演奏を聴きながら、楽しく上品にワインを飲んでいます。
彼等はワインを味わいにやってくるので、食べる物があまりありません。
酒を肴に、酒の肴を食べるのを常としている私は、こういうときに本当に、困ってしまいます。おいしいので後先を考えずに結局飲み過ぎてしまいます。真っ赤になって、心臓がドキドキするので、お水がほしいと言ったら、「サービスだ。」と高い方のガス入りの生ぬるいのをグラスに注いでくれました。ああ、私は氷のかけらが一つ二つ浮かんだ、きりっと冷たい普通の水がほしかったのに。顔で笑って心で泣いて・・・・、国際親善には実はこのような一こまも存在しますが、それも時と共に感動となり得るのがまた楽しからずや、といったところでしょう。
【補 足】 "ドイツ大好き"のページで ワインの話をもう少し
